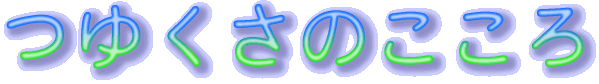
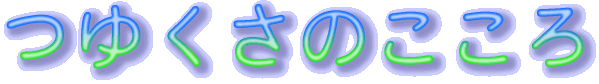
文章講座課題文 「においの記憶」 (1989年)
来年の春、小学校を卒業する長男の体から子どものにおいがしなくなった。
私は折にふれ、子どもと取っ組み合いながら、子どもの体に鼻をすり寄せて、ホックリとした子どものにおいをかぐのが好きだ。彼らには特有のにおいがある。何に例えることもできないが、母親にとって、我が子ゆえの好ましいにおいなのだと思う。
子どもに鼻をすり寄せるようになったのは、長男が生まれ、授乳を始めてからである。赤ちゃんの小さな体は、フンワリとしたおっぱいのにおいがする。何度ほおずりをし、何度抱きしめたことか。
乳離れし、外遊びが盛んになるころから、子どもの体からは「ひなた」のにおいとでも言うのだろうか、独特なにおいが漂う。まだ小学三年生の次男には、辛うじてこのにおいが残る。「親離れ、子離れ」という言葉があるが、抱きしめて、このにおいがしなくなるころから、そろそろ子どもの自立が始まるのであろうか。
私は、衣装箱の底に、我が子が乳飲み子であった時に着せた服を数枚残している。衣替えの季節が来るたびに取り出して、子どもたちを呼び、
「こんなの着ていたのにねぇ」
と話しかける。子どもたちが幼いころは
「わあ、それ、ぼくが着ていたの?今でもきれるかなぁ」
と喜んでいた彼らも、最近では
「やめてよ、そんなの出すの」
と言うようになった。母親の私はひとり取り残されて、それでも、ベビー服を手に、当時信じられないほど小さく頼りなげであった手足を思って感傷に浸ることしばしである。
次男の体からも、もうじき子どものにおいが消えるだろう。
捨てきれなかったオムツの束を、最近やっと近くの保育園へ寄付した。赤ん坊を抱きしめたパステルカラーの思い出は遠くなってゆく。