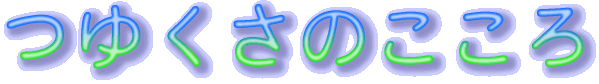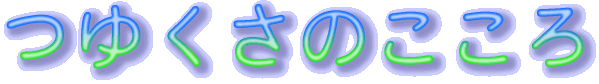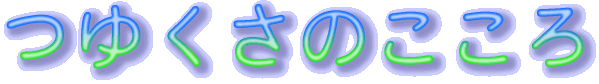
水のある風景
初夏の水田は、夜半、カエルの大合唱である。周囲を水田に囲まれた離れの部屋で、独りひっそり物思いにふけるには、この季節は向いていない。
ガッガッガッ、ゲコゲコゲッっと、あたりが静かであればあるほど、耳に障ってくる。片思いのあの人のことを心に浮かべ、うっとりしていると「ガッガッガッ・ケロケロ・ギョロギョロ・・・」 耐え切れずにガラリと窓を開け、押し殺した声で「ウルサイッ、ダマレカエルドモ」と、何度叱り飛ばしたことか。時には、やみ夜に黒光りする水面を、しばし、にらみつけていたこともある。
だが、何しろ多勢に無勢。何匹いるか知れない相手は、言う事など聞きもしない。「カエルの面に何とやら」。悩み多き娘に同情するデリカシーを、彼らは持ち合わせていなかったに違いない。カエルの顔がなんとも憎らしく思えたものである。
不思議なもので、あれほどウルサイと思った鳴き声が、20年近い歳月を経たいまでも、ふとした折にゲコゲコゲコッと頭のしんに響いてくることがある。時には、あの生演奏をもう一度聞きたいと思うことすらある。
カエルの季節は田植えの季節でもある。竹の定規を当てて、ヌポッと足を抜きながら後ずさりで早苗を植え込んでいく。泥田の作業は疲れも倍だった。
早苗が、30〜40センチほどにも育つころ、夏である。クーラーのない当時、青田をわたる風と、家の横を流れる用水路のせせらぎが涼しさを提供してくれた。
庭先に縁台を持ち出し、ふろ上りの涼をとる。家の前の田んぼには、細長い稲の葉の間に、露のきらめきかホタルか決めかねる光がチラチラとする。空にはクッキリと満天の星。
5月から9月にかけての私の記憶は水のある田園風景に重なる。その当時、水は自然であり、生活と共にあった。