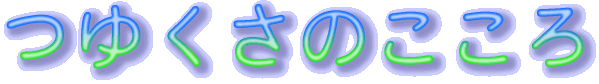
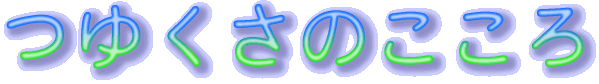
文章講座課題文 「雲」 (1989年)
田舎育ちの私は、子ども時分、ぼんやりと過ごす時には必ず、どこかにひっくり返っていた。百八十度の視界に広がる空に、雲の変身を目で追いながら・・・。
春、レンゲ草に埋もれて見上げた雲は、モコモコした羊のように、ゆったりと浮かんでいた。顔にレンゲの花がかぶさり、かすかな香りに鼻をくすぐられながら、次第に眠くなっていった。起き上がるころには、顔や全身にポツポツと黄色い花粉が付着していた。
冬は、ひなたぼっこが楽しみだった。農閑期には使わないむしろを家の南側に敷き、その上でゴロゴロするのである。ままごとをしたり本を読んだり。その揚げ句、本で顔を覆ってうたた寝となる。そんな時、弱い冬の日差しをさえぎる雲は癪のタネである。雲が太陽を隠すと寒さで緊張し、切れ間から日が差すと、ホッとして肩の力を抜く。そんな「メリハリのある」ひなたぼっこだった。
何となく、イソップ物語の「北風と太陽」が頭に浮かぶ。
高校生活最後の夏休み、「三畳」と呼んでいた文字通り三畳敷きの勉強部屋に仰向けになって、わらぶきの屋根越しに空を見ていた。
目が痛くなるほどの空の青さ。裏山の木立の上に、ムクッムクッと盛り上がる入道雲。それは、あふれ返る太陽に照りつけられ、自信満々、地の底からわいて来た姿だった。この日の光景は、入道雲とセミの声でワンセット。音の出る一枚の写真のような思い出なのだ。
入道雲の威圧に負けない気力と体力、それは、まさに若さだったのだと、最近つくづく感じる。
このところ、ひっくり返って空を見上げる機会を持たない。故郷から遠く離れたこの土地で、雲はどんな変化を見せてくれるのだろう。近くにある利根川の土手に横になり、つくづくと「今」の目で追ってみたい気もする。