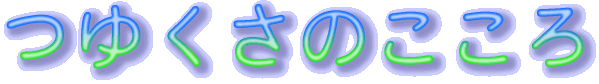
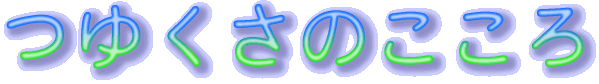
文章講座課題文 「香水」(1988年)
私は香水を使わない。香水に限らず、化粧品全てを無香または弱香にしている。独身のころには、二ナ・リッチの甘ったるい香りが好きで、コットンに含ませてしのばせたり、衣類の裏側に吹き付けたりしていたが、今考えると、ずい分無神経な使い方をしていたものだ。
結婚後間もなく、身につける香りは自分でかぐより、大部分は周囲の人にかがせてしまうものだと気が付いた。
新婚まもなくのころ、主人の使う男性化粧品の香りは私の鼻に新鮮だった。むしろ、好ましくさえあった。ところが、最初の子を妊娠し、ひどいつわりに悩むようになると、それは嫌悪の対象となった。何度も使用を中断してくれるように主人に頼んだけれど、私よりおしゃれな彼としては全面的にストップとまでは譲歩してくれなかった。
事の始まりは、妊娠と気付かずに吐き気に苦しんでいたある日、「悪い風邪かもしれないから病院へ行こう」と言った彼の思いやりからである。一両日、何も口にしていなかった私のために彼はナシをむいてくれた。そこまではうれしかったのだが、そのナシに彼の手から化粧品のにおいが移ってしまっていたのだ。せっかくだからと口に運んだ途端、私は、ムカムカとして洗面所にかけ込んでしまった。いまだに私はあの化粧品のきつい香りをかぐと、つわりの気分を思い出してしまう。それ以来、私は作られた香りになじめない。
実家の母は、あの食欲をそそるご飯の炊けるにおいにもムカついたときがあったそうだが、私はこちらの方は平気だった。ご飯のゆげだって、化粧品のにおいだって、人によっては避けたい時がある。
つけている本人が気づかないときも、「ひと瓶ふりかけたんじゃない?」と陰口たたかれるほどきつくにおえば、これはやはり目には見えないけれど、臭害という公害ではないだろうか。たかが香水、されど香水。香りの演出は、やはり相当むずかしそうだ。