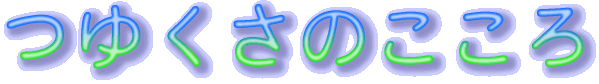
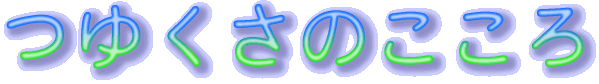
文章講座課題文 「米」 1989年
米は買って食べるものではなく、作って食べるものだ。農家出身の私は、いまだにその感覚が強い。生まれた時から米は当たり前のように身の回りにあった。秋の収穫時に一年分の自家消費米を除いて国に買い上げてもらうのだが、そうした換金作物というより、子供の私には、自家用米としての印象のほうが強かったのであろう。
もみすりをした玄米は、カマスに入れて蔵などにしまう。その中から適宜、適量を農協の精米所で白米にしてもらう。持ち帰った白米は、直径1メートル高さ1,5メートルばかりのブリキの円筒缶に保存する。その貯米器から当座の分量を米びつに入れて台所に置いた。米びつが空になって、何度か貯米器まで出しに行かされたことがある。いつだったか、長屋(実家で物置にしていた離れ)のカマスや貯米器の米を見ながら、これだけあれば食べることに不自由はしないだろう、と子供ながら妙に安心したことを覚えている。白いご飯さえあれば満足という人もいるようだが、実は、私は食卓のご飯に執着はない。むしろ、パンの方が好みである。しかし、生活を考えた時、米びつが満たされているか否かは、いまだに安心のバロメーターになっている気がする。
実家では、父が亡くなり、母は年老い、兄夫婦に農業を継ぐ意思は無いらしく、次々と水田は他人の手に預けられた。夫の実家も似たような状況で、結婚後定期的に送られてきていた米も、今ではどちらからも届かなくなった。子供は幼く、小食な夫とご飯を食べない私とでは食べ切れなかったほどだった。あれは本当に「有り難い」ことだったのだと今になって思う。親心というのは、十分に受けている時には感じないけれど、世間には外には存在しない、有り難いものなのだ。
現在、米の消費者の私が、気持ちはいまだに生産者に近いというのは我ながらおかしい。