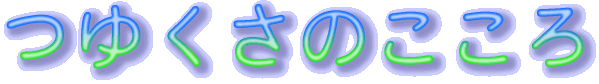
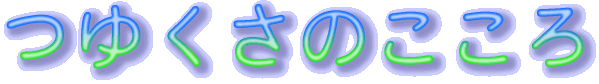
文章講座課題文 「年賀状」
暮れになると、私は年賀状を出す顔ぶれを頭に浮かべて、憂うつになる。思えば、夫の存命中は、年賀状のあて先で悩むことはなかった。夫の指示通りで済んだからだ。夫婦の親やきょうだいには、出すべきものとして毎年やりとりをした。たとえ、形だけであったにしろ、である。
夫が逝って三回目の今年の正月。やっと、世帯主として独自の判断をする心のゆとりが生まれた。暮れも押しつまった三十日に、あの顔、この顔を思い浮かべつつ、言葉を選んで、三十六枚の賀状を書き上げた。それぞれに、日ごろの感謝の念をこめたつもりである。
年が明けて一月七日現在、私の手元には四十枚余りの賀状が届いた。心待ちにしていたもの、意外な人からのもの、明らかに義理だとわかるもの、と様々である。
私には、どうしても受け取りたくない賀状がある。それは、夫の病中・葬儀後に態度のがらっと変わった親類縁者からのものである。彼らの目に触れる場所に住みたくない・・・これも、夫亡き後に私が田舎へ引っ越さなかった理由のひとつである。そんな彼らの一部から、今年も形式的な賀状が来た。何のぬくもりも感じないハガキを手に、私はため息をつく。
一方、去年一年間、私が誠心誠意でつき合ったと思っていた友人から賀状が来なかった。結局、そのつき合いは、私からの一方的な思い込みだったということだろうか。ヘビをデザインして、「プリントごっこ」で印刷した彼女の賀状の束を暮れに見せてもらった。その時、彼女の頭の中に私の名前はなかったわけだ。
人との一年間のつき合いに、判定を下してしまう年賀状のやり取りは、残酷なものだと思う。手紙を書くことの好きな私は、たとえ一枚の年賀状といえども心をこめる。義理で書くのは、大変つらい。
年末年始は、私の気分の最も浮き沈みの激しい季節でもある。
(1988年)