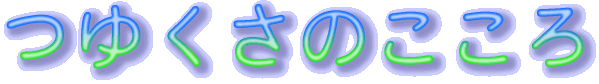
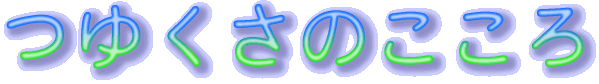
文章講座課題文「忘れられない味」 (1989年)
今の時代ほど果物の種類はなくて、しゃれたお菓子を口にする機会も少なかった小学生時分、私は、グミや木いちご、イタドリにスイバと野や山にある物をよく口にした。名前は知らないけれど、緑の皮に包まれた白く細長い、猫のしっぽのような感触の雑草の穂は、ガムのようにかんだ。そんな食べ物の中で、私はなぜか、山桃に執着している。
山桃の実は、黄緑色から暗赤色へと変化して熟してゆく。直径一・五センチくらいの丸い玉で、表面はザラザラとした突起に覆われている。数粒づつの実が、寄り添うように小枝の先になる。葉は、長円形で、十センチほどの長さだったろうか。木には、雌雄がある。
私の家の持ち山には山桃の木がなく、親がひと言ことわってくれた知り合いの山へ、山桃の実をとりに行ったことがある。女の子四人で、昼間も薄暗い山の中へ入って行く。黒々としたその木は、真ん中に雄、左右に雌が植えてあった。山や野を駆け回る女の子は、木登りも平気。登る者、下で待つ者。受け取った実は、スカートのすそを持ち上げ、カンガルーの袋のようにした中へ集めた。山桃の熟した物は大変崩れやすくて、家まで持ち帰ると、スカートは赤い果汁でしっかり染まっていた。
残念なことに、味の記憶は鮮明ではない。酸っぱいものが嫌いな私の好みに合ったのだから、相当、甘かったような気もする。山桃を口にした思い出は、そう多くはない。存分に食べたのは、自分の手でもぎ取って来たこの時だけだった。他人の山の生り物やキノコをとってはいけないことは、田舎の子どもには常識だった。
強い印象の残る山桃の実に、あれからお目にかかれないでいる。手に入らないものは、一層、恋しい。これを、郷愁と言うのだろうか。あの当時に比べると、豊富な食べ物に囲まれた最近の私。いたずらに、山桃が手に入ったところで「おいしかったんだ」という思い出に、水をさすだけだろうか。